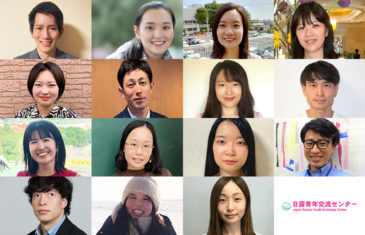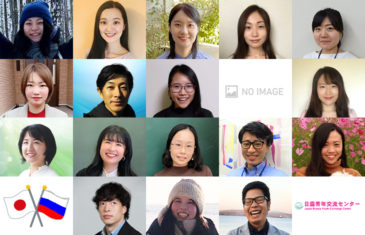-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2013 年度)
- 京都大学大学院文学研究科
博士後期課程
高田 映介
日露青年交流センター若手研究者等フェローシップを受けて、2013年10月からサンクト・ペテルブルグ国立大学でアントン・チェーホフの作品について研究を行っています。受け入れ先としてペテルブルグ大を選択したのは、イリノイ大学のチェーホフ研究者であるマイケル・フィンク教授から、同大には『一人は比較的若く活発な理論家で、一人はすでに高齢だが研究界の指導者的立場にある』二人のチェーホフの専門家がいる、と教えて頂いたのが最大の理由でした。最大の理由はそういうことだったのですが、実は、兼ねてより憧れに近い気持ちを抱いていた都市をこの目で見てみたい……というのも、モスクワよりペテルブルグを選んだ密かな理由でした。少し雑多になってしまうかもしれませんが、大学での授業の様子を中心に、思ったことや印象など滞在記として綴りたいと思います。
ペテルブルグ大学文学部はヴァシーレフスキー島にあります。2013年の10月に初めて足を踏み入れた時、建物は改修工事の真っ最中でした(でした、というか現在も最中です。そしてこうした工事がいつ終わるのかは、ロシアでは大抵『誰にも分からない』こととされています……)。筆者を研究生として受け入れてくれたロシア文学史学科は二階に位置しており、通常なら表玄関を入って目の前にある階段を上がっていけばいいのですが、初日は工事のためにトイレ(!)を通り抜け、裏手の階段から大回りして行く必要がありました。迷路のように入り組んだ道筋で、覚えられるだろうかと焦った記憶があります。現在は階段部分については工事が終了し、立派な両階段を使用できます。кафедра(講座、学科が直訳ですが、日本の大学院の感覚で言うと「研究室」でしょうか)がずらりと並ぶ二階の廊下も重厚な雰囲気で、大学の歴史の深さを思わせます。

修復が完了した両階段
がっしりした堅固さを漂わせるこれらの部屋の中で行われる授業も、やはり同じように歴史に根付いたものでした。筆者の指導教授となることを了承していただいたアンドレイ・ステパーノフ教授(冒頭の話で言うと前者にあたります)の特別講義『チェーホフとその時代』は、定本とされている研究書を週に一冊のペースで読み、これまでの研究の流れを振り返ることから始まりました。ロシア人の学生たちに混じって「大先輩」たちの本を改めて読み直すうちに、先行する研究を受けて次の研究があり、さらにその後に今の自分の研究もつながるのだし、むしろ繋がらなければならないのだという基本を思い出しました。文学史観の遵守、個別作家の枠に収まらずに広くロシアの作家全体を視野に入れ、比較しながら分析を作り上げていく手法、日本の文学研究に一般に見られるのとはまた違うロシアのアカデミズムを、授業を通じて感じることができました。語弊があるかもしれませんが、ペテルブルグ大学にはいろいろな意味で昔風の研究スタイルがまだ残っているように思います。人文系の学問に対する風あたりの厳しい昨今の状況だけに、なんだか頼もしいものを感じました。たとえば指導教授と学生の関係にしても、筆者の場合ですが、「師匠」であるステパーノフ教授が「来週までにこれを読んでおいで、要綱を書いておいで、これこれの作品の分析をこれこれの観点からやっておいで」と言いつけたことを、「弟子」は必死にこなして稽古をつけてもらう…といった具合でした。一方で教授は、「過去はそれとして踏まえた上で、自分固有の問題の核心を見つけなくては」ときっぱりとおっしゃって、言語的実証主義を掲げつつ、修辞学、記号学、社会学などの理論を自在に駆使しながらご自身の先鋭的な分析を作り上げてもいる人です。週に一度会って色々なテーマについて話すうちに、筆者の中でも、これまでは思い至らなかった、かといって無根拠なのではない、新しい分野と自らの研究との接点が浮かび上がってきました。

アンドレイ・ステパーノフ教授
残念ながらステパーノフ教授は6月に中国への長期出張に立ってしまわれたのですが、ある意味ではそのおかげで、もう一人のチェーホフ研究者であるイーゴリ・スヒフ教授からも指導を受ける機会を得ました。スヒフ教授は筆者の博士論文計画にじっと耳を傾けられた後、関係がありそうないくつもの参考文献の名前を即座に挙げられました。そしていたずらっぽく目を細めながら、「私はもう200から著作があるけれど、まだまだ言い足りない。だから貴方にも頑張ってもらって、足りない分を埋める手伝いをしてもらわないとね」と言い、「とはいえロクでもない研究なら追い払うけどね!」と笑い、それからまた真剣な顔つきで「貴方のテーマでは、フォークロアとチェーホフの関係というところが私には興味がある」と。日本で、著者近影で見ていたその人を目の前にした緊張感のせいか、この時のことは強く印象に残っています。こうした二人の教授の指導のおかげで、奇しくも大学の授業スタイルと同じく、過去に根差す方向と、過去を踏まえて未来へ向かう方向の両方を含み得るようなテーマが、筆者の中にも見えてきつつあるように思います。
ところでどうやら、お芝居にもそんな傾向が見受けられたようです。専門であるチェーホフはもちろん、シーズンの間に見られるものはなんでも見てやろう、と決めてかかって、『かもめ』『ワーニャおじさん』『三人姉妹』『櫻の園』の四大戯曲はもちろん、『罪と罰』『白痴』に『持参金のない娘』まで、余暇を兼ねてせっせと足を運びましたが、毎回感想は異なるものだったにせよ、全体としては伝統的な解釈に基づいて演じられる中のどこかに、必ずいつも何かしらの新しい試みが行われているのが感じられました。アレクサンドロフスキー公園の中にある劇場で『罪と罰』を見た時は、忠実なテクストを用いつつ、オリジナルにはいない進行役を設定することで、長大な原作を濃密に凝縮した形で見せることに成功していました。考えてみれば、18世紀の建物でさえ「新しい」と言い切ってしまうこのペテルブルグという街にとっては、過去を見ながら未来に向かう姿勢はごくごく当たり前のものなのかもしれません。そういう街に暮らし、博士論文についてじっくりと考える時間を持つことはできたのは本当に得難い経験でした。今後もペテルブルグ大の学びの姿勢を胸に、大局的な視野に立つことを忘れず研究を続けていきます。最後に、フェローとして採用していただき、色々なサポートをしていただいた日露青年交流センターに、感謝の意を表します。
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.