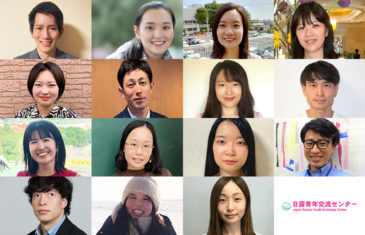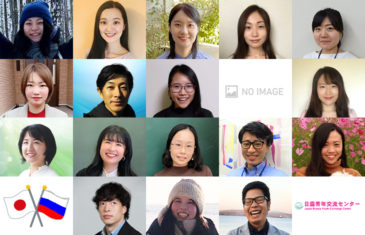-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2011 年度)
- 北海道大学スラブ研究センター
安達大輔
日露青年交流センター若手研究者等フェローシップを受けて、2011年12月31日から一年間の予定でモスクワのロシア国立人文大学で研究をおこなっている。モスクワ大学が抜群の知名度を誇る場所で滞在先としてこの大学を選んだのには相応の理由がある。まず世代の近いロシア文学研究者が数人こちらで学位を取得しており情報を得やすかったこと、そして筆者自身もすでに長期滞在を経験した結果、研究テーマの選択をはじめとする受け入れ環境の面で比較的風通しのよいことを実感していたためである。鳥山祐介先生(注1) の指導教官であったゾーリン先生はすでにオックスフォード大学へ転出しているが(注2)、鴻野わか菜・大森雅子両先生を指導したマゴメードヴァ先生は現在も精力的な活動を続けている。また欧米圏で活躍する研究者との交流が盛んなのも特徴で、「国文学」の枠組みを開いていくような研究会が多く開かれている。これまでとくに強い印象を受けたものとしては、ジヴォフ先生(カリフォルニア大学バークレー校)による「ロシア正教会における告白の儀式の制度化過程」をテーマとした報告、そしてボリス・ガスパーロフ先生(コロンビア大学)がヨーロッパのロマン主義詩学についておこなった射程の広い連続講演があり、研究を進めてゆくなかで大きな刺激となっている。
ただ、今回の研究滞在の目的ははっきりしていた。ここで教鞭をとっているユーリイ・マン先生のもとで研究することである。
ユーリイ・マン――19世紀ロシアの作家ゴーゴリについては日本でも広く知られていると思うが、その研究史のなかでこの名前は特別である。ソ連時代の1978年に発表した『ゴーゴリの詩学』は現在でもなお最重要文献のひとつとされ、秦野一宏先生によって日本語訳もされている(『ファンタジーの方法:ゴーゴリのポエチカ』、群像社、1992年。計3章ほど省略されている)。内容と研究史上の位置について解説した訳者あとがきも付いているので、興味をもたれたら手に取っていただきたい。そこでも触れられているようにマン先生は1983年、ゴーゴリ・シンポジウム参加のために来日もしていて、そのことはいまでもたびたび話題にのぼる。また海外から訪れる研究者には敬意とあたたかさの両方をもって接してくれる。これもゴーゴリの書いたものを一人でも多くの人に読み研究してほしいという思いからだろう。4月1日の作家の誕生日に合わせてモスクワでは毎年ゴーゴリ読者の集まりが開かれているが、2012年は報告をした井上幸義先生と親交を深めていた。
マン先生の研究のどこが魅力的なのか。その紹介は「簡単に」という類の作業ではありえないし、かといって本格的に取りかかれば学術的な形で発表すべきものである。ここでは今回の滞在で接した限りでの印象を記すにとどめておきたい。
先生の仕事は①ゴーゴリという作家の研究②19世紀前半から中期にかけてのロシア文学全般の研究という、二つの中心からなる楕円に思える。この二つの中心は密接に関係しあいながら、合わせ鏡のように互いのなかで互いを反映し合っている。
その研究には一貫した方向性が感じられる。『ゴーゴリの詩学』を例にとると、刊行当時のソ連では、ゴーゴリはロマン主義の作家なのかそれともリアリズムかという議論があった。先生はこの枠組み自体をイデオロギー的(で文学研究としては粗雑)なものとしてとらえる。ゴーゴリ作品に変化や危機が感知されるのは間違いない。しかしその分析の道具として、ロマン主義やリアリズムといったレッテルはあまりにも茫洋としている。だから幻想や現実、笑いや涙といった区別に重ね合わせてロマン主義とリアリズムを理解する「常識」からゴーゴリの作品をいったん切り離す。そうしておいて、そこで問題になっている危機や変化を、文体のさまざまな特徴(「詩学」)からあらためて考え直してゆくのである。
こうした姿勢は、『ロシアの哲学的美学(1820年代から1830年代)』(1969年)、『ロシア・ロマン主義の詩学』(1976年)、『スタンケーヴィッチのサークルで』(1983年)、『アクサーコフ一家』(1992年)といった一連の研究につながっている。そこでは社会主義リアリズムの前史として19世紀文学をとらえる当時のメジャーな視点からは漏れてしまうような作家や思想家たちに光があたっている。
近年も精力的に著作を発表していてそのすべてを紹介することはできないが、とくに重要だと思えるものをあげておきたい(なおロシア語の文献ではあるが、2009年に80歳を迎えたことを記念して人文大学出版局から刊行された論集『ロシア文学の詩学Поэтика русской литературы』には、巻末にそれまでの全業績のリストが掲載されている)。
ゴーゴリの学術的な伝記研究が少ない日本の現状を考えると、現在もっとも信頼度の高いものである伝記三部作はとりわけ貴重であり、翻訳が待たれる。まず2004年に第一部と二部の合本が『ゴーゴリ 労働と日々:1809-1845年』として出版され、2009年の第三部『ゴーゴリ 道の終わり:1845-1852年』をもって完結した。2012年には改訂を加えた上で一部・二部が分冊されて、コンパクトになっている(『ゴーゴリ 第一巻 始まり:1809-1835年』『ゴーゴリ 第二巻 頂点で:1835-1845年』)。
ゴーゴリは改稿を重ねた作家であったが、マン先生も自著の増補改訂に熱心である。すでに述べた『ゴーゴリの詩学』は2007年に第4版を数えた。タイトルも『ゴーゴリの創作:意味と形式』に変わり、分量は700頁を超えてページ数で言えば初版のおよそ二倍になる。1998年には『ロシアの哲学的美学』が改版された。『ロシア・ロマン主義の詩学』は『ロシア・ロマン主義のダイナミクス』(1995年)、そして『19世紀ロシア文学:ロマン主義の時代』(2001年)へと発展を遂げ、2007年にはさらに改版されている。
また2011年にはベールイの著作『ゴーゴリの至芸』が再版されたが、先生はこの1934年の研究を非常に高く評価していて、序文を寄せている。
ロシア・科学アカデミーによって現在刊行が進んでいるゴーゴリ全集の編集長としての仕事にも言及しておきたい。すでに1巻(第一文集『ディカーニカ近くの村での夜ごとの話会』など)、3巻(第三文集『アラベスク』など)、4巻(『検察官』など)が出版され、2013年1月には『死せる魂』第一部を収録した7巻が手に入るようになっている(テクストと注釈で二冊に分冊!)。これは1937年から52年にかけて刊行された14巻の旧全集の新版であり、最終的には23巻を数えるという。財政的な事情で刊行ペースは遅々として間歇的ですらあるが、注釈を中心に豊穣極まりない内容を持つものであるから、続刊が切望される。

新刊『記憶は幸せ、そして記憶は痛み……回想、資料、書簡』とともに。個人的なエピソードが集められたおそらく初めての本である。それらが常に研究と結びついている点が先生らしいが、ソ連から現在に至る文学研究の歴史には時代性が色濃く影を落としていて、結果としてそれぞれの文章がガラスの破片に映すように時代の姿を見え隠れさせる。
先生の分析を読んでいると、文学作品が文のかずかずによって織り成される綾であることを実感する。各々の文は明快な論理で書かれているが、結論として全体を俯瞰しようとすると複雑なモザイクをなすので一言で説明することなどできなくなる。膨大な先行研究を遺漏なく参照して「ここは注目すべきだがここが違う」「それではこの意見はどうか。この点では正しいが、この点が違う」というように、肯定しながら言葉の微妙な陰影を浮かび上がらせる、そうした作業が繰り返される。「文学とは何か」を性急に定義することによってではなく、分析の対象となっている文章とそれまでに蓄積された研究とのあいだのかなり微細な空間を明視する実践によって、いま分析されているものが紛れもなく文学として私たちに伝わったものであることが確かめられてゆく。したがってその著作にわかりやすい図式はない。
このスタイルは授業でも変わらない。人文大学では「1800年代から1830年代のロシア文学史」(前期)「テクスト校訂学」「ロシア文化史」(後期)それぞれの講義と、通年のゼミ「世界文学のコンテクストにおけるゴーゴリ」が開かれている。流れを大事にしながら淡々と丁寧に語り進めるかのような文章は、講義のように書かれているのかもしれない。講義中の声を重ねることでその文章をより身近なものとして感じられるようになった、気はする。
授業では、この偉大なゴーゴリ研究者が「ゴーゴリの作品はまだまったく分析し尽くされたとは言えないし、そうなることはありえません」という一言に込めた確信が印象的だった。先生にとって文学作品は明らかに特別である。プーシキンの『エウゲーニイ・オネーギン』をとりあげた講義では、この作品は当時のロシア生活が書き込まれた「百科事典」であるという有名な言葉を批判的に引用しながら、いくつかの箇所を当時の歴史状況と比較して相違点を浮き彫りにする。きめ細かい検証にときおり「神ハ細部ニ宿ル」「一般化してはどこにも行けません」というコメントがはさまれる。それは20世紀初頭、「文学は社会を描写する」といったタイプの当時のいささか粗雑な社会学的読解に対して、文学作品および文学史は相対的に自律したシステムであると主張したロシア・フォルマリストからロートマンまでの文学史研究のひとつの側面を、系譜として思い起こさせもするのである。
「ポエジーはポエジーである」――先生がよく口にするゴーゴリの言葉である。しかし文学以外にもさまざまなメディアによって生活が成り立っている現在、文学は文学そのものであって、社会から相対的に独立した視点を持っているという主張はどれほどの有効性を持っているのだろうか?次のような疑問はありうる。このテーゼは既存の文学研究の制度に自閉する態度そのものである。文学や文学研究が政治と無縁でないどころか、その一部をなしていることは今日では自明である。徹底的に作品の細部に拘ることは、文学作品が社会から独立しているという主張そのものを可能にする社会的な諸条件から目を背けることではないか、と。
しかし、そもそもこの言葉はテーゼなのだろうか。
ここからは完全に推論である。
先ほど、先生にとって文学作品は文章の綾ではないかと書いた。綾取りの綾は形をとっては崩れ、絶えず動き回って別なものになる。先生にとって文学作品が特別なのは、それが形や意味をさまざまに変えながら、「反復されうる」という力をもつからだ(「ポエジーはポエジーである」)。というか、それは反復によってはじめて作品となる。文学作品があなたに届くのは、誰かから誰かへ、ある世代からある世代へ、ある国民からある国民へ、あるグループからあるグループへ、ある性からある性へ伝わる偶然が積み重なったからであって、そのままの文学作品というものはどこにも存在しない。
先生は文学作品の力を、それを伝える人々の行為を、とても信頼しているのだと思う。そして、逆説的なようだが、このプロセスを人々にとって危ういものともまた見なしているのではないか。文学研究の「客観性」を強調する言葉に、反復への信頼と危惧の背反が滲む。文学作品の反復が、積み重ねや伝統、さらには制度となる過程で変わってしまったものと変わらないものを、ぎりぎりの地点で見定めようとする執念のようなものを筆者は感じるのである。その極限点に、空白としての場所、研究の積み重ねのただ中で自分を異なったものにする「ポエジー/ポエジー」のすきまが、文学の可能性として見いだされる。文学作品に意味と形を与える人々の思想や感情、欲望や恣意、言ってしまえば行為や生を透かして見る透徹した眼差し。それは感傷や情緒とはまったく違うが、それでも人間の営みへの、ついには信頼としか言いようのないものだろう。
文学作品の内も外ももはや過去の概念なのだろうか?すべてはべったりと広がる細部の堆積であり、それを拾い上げる作業が残されているだけなのか。だとしたら、文学の境界を執拗に問い続ける先生の姿勢は古臭いのだろうか?
筆者は心を打たれるし、そこに文学研究における世代差という安易な「解決」を与えたくはない。もう一つ講義での言葉を引用したい。「『エウゲーニイ・オネーギン』は問題であって、問題を提出しているのです。解決するのは私たち読者です」。問題をつくること、それは反復をトートロジーに還元しないことなのかもしれない。この時代に「文学とは文学である」と誇り高く告げることは、何を問うているのか。あなたに伝えられたものが内と外を生み出すそのときの震えを問い続けることでなければそれは何だろうか。文学研究という枠組みなど必要ないと言い切ってしまうのなら話は別だが、文学研究者を名乗る限り、筆者はこの緊張感をつくりだすことのできる研究に魅かれるのである。
注1:「ロシア国立人文大学大学院(モスクワ)における留学体験報告」『日本ロシア文学会関東支部報 』第 23号、2005年、23―27頁は、海外の大学院で研究することについて自覚的に考えるための参考にもなる。
注2: オックスフォード大学での研究中ゾーリン先生を受け入れ教官としていた乗松亨平先生による滞在記が、以下のサイトで読むことができる。http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/itp-hp/report/report009.html
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.