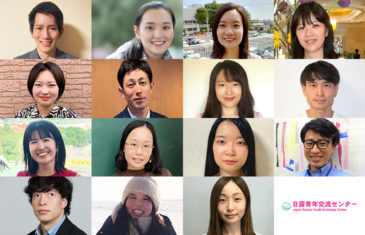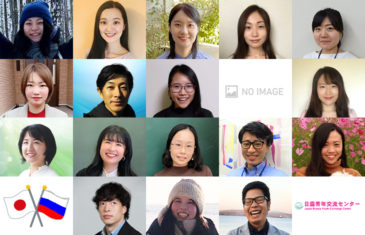-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2012 年度)
モスクワのハルムス劇 小澤 裕之
2013年4月、モスクワではダニイル・ハルムスの作品や人生に題材を取った演劇が幾つか上演されています。私は4つの舞台を観劇する機会を持ちましたので、その印象をここに記したいと思います。
演劇芸術学校(Школа драматического искусства)付属の劇場にて上演されたのは、ハルムスが1930年に書いた戯曲『グヴィドン(Гвидон)』。この作品は、前年に別れたばかりの妻エステルに捧げられたものであり、詩人の言語実験によってテキストが不可解にされているものの、全体としては恋の物語として把握することが可能です。ハルムスは1920年代後半に未来派の衣鉢を継ぐザーウミ詩人としてその作家活動を開始、そのテキストからはやがて典型的なザーウミ(超意味言語)が減少するものの、テキスト自体はしばしば難解で意味の画定は困難です。1930年の段階でもまだその傾向は残っていました。しかしながら、「オペラ」と銘打たれた今回の上演(オガリョフ/グルシコフ演出)において、仮に意味内容は不可解であっても、ハルムスの作品は音楽として楽しむことができる、ということが高らかに謳われたように思います。意味のある台詞はもちろん意味のない台詞までもが、コーラスに乗せられると、ときに陽気でときに悲しげなメロディとなって劇場内にこだまし、観客の感情を刺激します。舞台-客席は「円柱型」であり、中央の舞台の周りを客席がぐるりと囲んでおり、それは垂直方向に3層にわたります(つまり3階建て)。おまけに舞台自体も上下に移動、段々と奈落へ下がってゆき、最終的に再び元の高さに戻ります。この「天地の往還」という演出あるいは構造と『グヴィドン』のテーマとの関連性については一考の余地がありますが、「意味との闘い」を祈ることで幕を開けるこのオペラにおいては、それは恐らく副次的な要素であり、この舞台で前景化されていたのはあらゆる意味を後景に追いやる心地よい歌とリズムなのでした。

演劇芸術学校の内部。吹き抜けが心地よい、モダンで洗練されたデザイン
ハルムス作品と音楽との親和性の高さについて、彼の友人ドゥルスキンは次のように記しています。「リーダ(ドゥルスキンの妻)が言うには、ハルムスの『男が家を出ました』はベートーヴェンの『マーモット』に合わせて歌うとすばらしく、まるでベートーヴェンが『マーモット』をハルムスの詩のために書いたと思えるくらいらしい。タマラ(友人リパフスキーの妻)が言うには、ハルムスは『マーモット』が好きだったそうだ。彼がこの詩を『マーモット』に合わせて書いたというのは、十分にありえる話だ。(中略)多くの詩人たちにおいては、詩というものはまず初めにリズムやメロディの音として発生し、それからテーマや言葉が現れるらしい。恐らく、この詩もそのように発生したのだろう。『マーモット』のメロディはハルムスの詩になったのだ」。
そもそも『マーモット』はゲーテの詩にベートーヴェンが付けた音楽ですが、ドゥルスキンによれば、それはハルムスの詩とも親和性が高いのです。
ところで、この『男が家を出ました』という詩は1937年に書かれましたが、男が家を出たままそれきりどこかに消えてしまった、というこの作品内容は、スターリンの粛清が猛威を振るう当時のレニングラードの状況を風刺しているとも取れ、実際ハルムスはこの作品以後、出版の機会を失います。そして1941年、まるでこの「男」のようにハルムスは忽然と姿を消し(警察に逮捕されたのです)、その翌年に監獄病院で死去しました。したがって、この詩はハルムスを始めとする多くの粛清された作家の運命を凝縮しているとも言えるわけです。そのような詩が幕開けの合図となったのは、ロシア演劇学校(Институт русского театра)付属の劇場で上演されたハルムスの芝居です。

ロシア演劇学校の外観
«Хармс…Храм…Хам…Ха…Х…» と題されたこの芝居(モロトコフ演出)は極めて祝祭性が高く、陽気にして悲愴、下劣にして崇高であり、アンビヴァレントな要素を一緒くたに孕んだ混沌としたものでした。『転げ落ちる老婆たち』を始めとするハルムスの様々な作品が断片として演じられ、芝居全体はさながらパッチワークのようです。その「断片」は長閑なものもあれば残酷なものもあり、明るい笑い話もあれば艶笑話もあり、賑やかなものもあれば陰鬱なものもあり、あるいはそれらの混成もあります。
興味深いのは、舞台に設置された「ХАРМС(ハルムス)」という名前のブロックが、それぞれ「Х」「А」「Р」「М」「С」と一文字ずつ書かれたブロックに分解され、芝居の進行に従って、それが「ХРАМ」や「ХАМ」に、そして「Х」に縦棒を一本足して「Ж」に再構築されることです。これは恐らく、ハルムスの作品や人生を解体し再構築するこの芝居の企図を表現しているのでしょう。「ХРАМ」が「寺院」を、「ХАМ」が「下劣」を、そして「Х」あるいは「Ж」が単なる音だけを表すとすれば、「ХАРМС(ハルムス)」は崇高なものと下等なものとに分解/再構築され、ときには何かを意味することすら止めてしまうのです。そのような様々な要素の混合から「ХАРМС(ハルムス)」は出来ていると言ってもよいでしょう。この舞台で再現されたハルムスの人生は実に多義的で、観客は彼の色々な側面を見ることになります。悲劇的に幕を開けたこの混沌とした祝祭的な芝居が静謐の内に終わるとき、私はハルムスの駆け抜けた激動の20世紀前半を思い、その流星のような生涯に思いを馳せ、深い余韻に浸りました。
同様にハルムスの様々な作品を素材にして舞台化したのが、ブルガーコフ劇場(Театр им. М. А. Булгакова)の芝居「三人でハルムス(Хармс втроем)」(監督はロガチョフ/ネグルツァ/アロニン)です。これはロシア演劇学校のハルムス劇よりも全体的に軽やかで、喜劇的です。ハルムス作品の内容をそのまま舞台に移すというよりは、舞台化する際に作品を相対化して批評的な距離を取っているように見受けられました。ロシア演劇学校においてはハルムス作品の登場人物をそのまま役者が演じているのに対して、ブルガーコフ劇場ではハルムス作品を巡って新たに創出された役を演じていると言えばよいでしょうか。つまり、役者がハルムス作品を生きるのではなく、ハルムス作品と一定の距離を保ちつつ、あるいはそれを茶化しながら、演じるのです。この距離感は、演出家や役者のハルムスに対する批評的な距離から生まれたものでしょうが、それは観客とハルムスとの間に批評的な距離を作り出すことにも成功しています。したがって、この舞台は観客をハルムスの時代に引き戻したりその苦楽を追体験させるというよりは、ハルムスについて冷静に深く考える契機をもたらしてくれるものです。ロシア演劇学校の芝居が「ハルムスの劇」であったとすれば、ブルガーコフ劇場の芝居は「ハルムスについての劇」であると端的に表現できるでしょう。

劇場/博物館内にあるブルガーコフの銅像
ブルガーコフ劇場は、ブルガーコフの家博物館の中に設けられています
最後にユーゴザーパド劇場(Театр на Юго-западе)について。この劇場は日本でもよく知られていますが、ハルムスの芝居(「みんな走って飛んで跳ねて…(Все бегут, летят и скачут…)」)は2007年から上演されています(ゴルシコフ演出)。子ども向けの舞台であり、私が足を運んだ日は、実際のところ観客のほとんどが子どもたちでした。小さな子は親と、より年長の子は友達と一緒に来ていたようです。そのためか、ここではハルムスの喜劇性ばかりが前景化されていました。意味を無化する音やリズムも悲劇性もなく、また批評的な距離を取ることもなく、ただ愉快で賑やかなドタバタが舞台上で繰り広げられていたようです。子ども相手の一種のショーと見るのが適切かもしれません。もちろん子ども向けの芝居だから悪いということはありませんが、今回の芝居は私には少し物足りませんでした。

ユーゴザーパド劇場の入り口正面
このように、4つの舞台にはそれぞれ個性があり、現代のロシアでハルムスがいかに多様に解釈され、且つその中で今も豊かに息づいているか、ということをそれらはよく示しています。私の観たこれらの劇場は常にほとんど満席であったということは、最後に付け加えておく価値があるでしょう。
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.