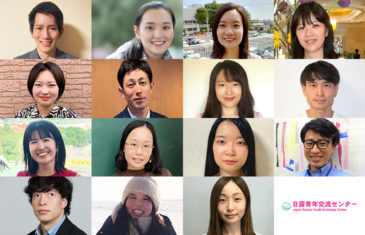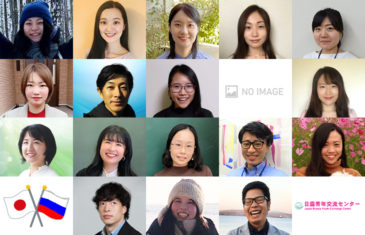-滞在記- 若手研究者等フェローシップ( 2011 年度)
- 北海道大学大学院文学研究科
ウラジーミル・ソローキン氏とお会いして 松下隆志
2012年9月9日、その日はあいにくの小雨模様で、筆者は約束の午後二時にモスクワの有名レストラン「カフェ・プーシキン」前にやってきた。店の前の道路には高級車が次々に止まり、まるでどこぞの高級ホテルのように黒服のベルボーイたちが客の世話を焼いている。どの車からその人が降りてくるのだろうと今か今かと首を長くして待っていたが、意外にもその人はメトロ駅の方角から一般人のようにふらりと徒歩で現れた。
.jpg)
ロックミュージシャンのように横に撥ねた灰髪、紺色のジャケット、青いジーパンを身に纏った長身の男の名は、ウラジーミル・ソローキン。ソ連時代はアンダーグラウンド作家として西側で名を馳せ、ソ連解体後はロシア版ポストモダンの最も過激な作家として国内でカルト的な人気を博した、現代ロシア文学を代表する作家の一人である。すでに五十代後半だが創作意欲は旺盛で、新作は発表されるたびに必ずロシアの文学界にセンセーションを巻き起こしてきた。
そんな伝説的な作家と差し向かいでランチを共にする僥倖に巡り会えたのは、筆者が北海道大学スラブ研究センターの望月哲男氏と共同で翻訳した氏の長編『青い脂』の出版がきっかけだった。氏とはすでに2012年3月にデンマークのオーフスで行われたカンファレンスで知り合っていたのだが、筆者が今回ロシアに滞在していたこともあり、またとない機会なので、ぜひ面会して日本語の著作を手渡したいと考えていた。メールで連絡を取ると氏は快く了承して下さり、『青い脂』を手に一路北の都サンクトペテルブルグから首都モスクワへと急行した次第である。なお、氏はかつて「現代ロシア文学のモンスター」と評されたこともあり、その作風のマニアックさから作者もとんでもない変人に違いないと思っている人が多いようだが、本人は非常に穏やかで礼儀正しい紳士である。
一階の窓際の席について注文を済ませると、早速持参した『青い脂』を著者に贈呈し、「アリガトウゴザイマス」と日本語で礼を述べていただいた。「マンガっぽい」と、表紙のデザインがいたく気に入ったご様子。グラスを合わせて「脂」に乾杯すると、本の表紙に少量のウォッカを垂らすという聖化の「儀式」を行った(氏の解説によると、この「儀式」は昔ロシアの軍人が受勲した際に行われたものだそうである)。
それから氏はこの「カフェ・プーシキン」の由来についても話した。レストランが開業したのはちょうどオリジナルの『青い脂』が世に出た1999年で、内装からウェイターの制服、メニューに至るまで、すべて詩人プーシキンが生きた19世紀を再現している。まさしく「ポストモダン・レストラン」というわけで、『青い脂』の刊行を祝うにはうってつけの場所だろう。
最初に出されたのはシチーで、ロシア料理を代表するキャベツのスープ。上にパンを載せた形で出された。飲み物はクワスを飲ませたいようだったがあいにく品切れで(ロシアではよくあることだが)、赤いモルスを飲んだ。
すでに十年以上前になるが、ソローキン氏はかつて日本に滞在していたことがあり、話題も自然と当時の四方山話になった。氏は吉祥寺に居を構え、「ガイゴ」(東京外国語大学)で二年間ロシア語教師を努めた。滞在中に京都や広島など日本中を旅行したようで、カラオケにも行ったらしい。当時のJ-POP事情にも精通していて、椎名林檎や宇多田ヒカル、浜崎あゆみなどのことを覚えていた。日本の院生に連れられてSMAPのコンサートにも行ったこともあるそうだ(日本の頃の体験は後の二三の短編で生かされているほか、最近までコラムニストを務めていた「スノブ」という雑誌のブログで日本に関するエッセイが読める)。
筆者が札幌住まいということもあり、話は北の大地のことにも及んだ。氏は夏と冬に二度シンポジウムで札幌を訪れたそうだが、特に記憶に残っているのは冬の札幌だとのこと。温泉に浸かり、新鮮な寿司と蟹を食べ、その後で巨大な雪の彫刻を見た(おそらく「雪まつり」のことだろう)。ちなみに、ビールは「キリン」が好みだそうで、氏によると日本のスラヴ学者は普通の人間より酒が強いそうである(残念ながら筆者は例外のようだが……)。
二杯目は札幌に乾杯した。
それから話題は肝心の『青い脂』に。未読の方のためにあらすじを書いておくと、これは近未来のロシアを舞台にした一種のSF小説で、ロシア作家の創作活動からのみ得られるという「青脂(せいし)」という特殊な物質をめぐる破天荒な物語だ。ロシア語に大量の中国語や造語がミックスされた奇妙な文体、ドストエフスキーやトルストイなどの作家クローンが生み出す奇怪なパロディー作品群、パラレルワールドのソ連・ファシズムドイツを舞台にしたスターリンとヒトラーの攻防など、ハイライトは無数にある。ロシア文学好きのみならず、外国文学愛好家の方にはぜひ一度手にとっていただきたい。
1999年にオリジナルが出版されたときの国内の反応を訊ねると(とはいえ当時本人は日本にいたのだが)、とにかく「爆発」とでも形容すべきものすごいスキャンダルだったらしい。良識派の批評家連は「古典に対する冒涜」と罵り、騒動はプーチン支持の青年団体「ともに歩む」との裁判沙汰にまで発展した。彼らは『青い脂』をポルノグラフィと訴え、挙げ句の果てにはボリショイ劇場の前に巨大な便器を設置してそこに氏の著作を投げ捨てるという「パフォーマンス」まで行った。最近ではプッシー・ライオットが教会を侮辱したとして逮捕された件が記憶に新しいが、今なお文学の権威が高いロシアでは古典作家に対する過激なパロディもまた一種の「聖物冒涜」と受け取られかねないのだ。
氏に作家クローン作品の中でどれが気に入ったかと訊ねられたので、個人的な好みとしてドストエフスキーとプラトーノフを挙げておいた。氏は自作の訳者たちによくこの質問をしているそうだが、答えにとくに決まった傾向はないそうだ(日本で読者投票でもやってみたら面白いかもしれない)。蛇足ながら、翻訳にもっとも苦労したのはナボコフのパロディだったと言うと、ありがたいことに作者自ら解説をしてくださった。氏によると、これは「ナボコフというリンゴを握りつぶして汁を全部搾り出し、粉々になった残骸をぎゅっと凝縮したもの」だそうだ。作者なのだから当然といえば当然かもしれないが、いかにも氏らしい直感的なたとえで、このコメントを本の解説に載せておけばよかったと思う。
続いてメインディッシュのカツレツがサーブされる。ロシアでこれほど美味なカツレツを食べたのは初めてだった。舌の上で蕩けるというのはこういう感じを言うのだろう。
次に現代文学の話になった。日本の作家だと氏は村上龍派で、春樹の方にはあまり関心がないらしい。他に安部公房の『砂の女』や『箱男』もご存知だった。日本の現代作家のおすすめを聞かれたので中原昌也氏をレコメンドしておいたが、誰か翻訳してくれないだろうか……。
また、筆者は現代ロシア文学を専門にしているので、ついでに現代のロシア文学についてどう思うかも聞いてみた。氏によると、注目すべき作家はいるものの、残念ながら若手作家の中に「スター」と呼べるような作家はいないそうだ。とはいえ、最近のものではЕлена Бочоришивилиという作家の«Голова моего отца»という作品がおすすめだそうで、これは後日読んでみたい。
それから何杯ウォッカを飲んだか記憶してないが、およそ二時間ほど夢の様な時間を過ごさせてもらった後で店を出た。奥様が近くまで車で迎えに来ているというので、レストランの前の公園を通って歩いて行く。ソ連時代から長らくモスクワ郊外に住んできた氏によれば、今のモスクワは街の個性を失ってしまったそうである。広い道路はたえず車で溢れかえり、とても散歩に適した場所とは言えず、もはや街というより「ターミナル」みたいになってしまったと嘆いていた。筆者が現代ロシア文学を読んでいても、資本主義化したモスクワのグロテスクな側面を強調する作品が非常に多いように感じられるのは確かだ。
スズキの車で迎えに来た奥様のイリーナさんにも自己紹介させていただいた。音楽家ということだが、ソローキン氏同様、スノッブなところは少しも感じさせない柔和そうな女性だった。今度は雪の札幌で会いましょうと言って別れた。日本で氏の来日を心待ちにしているであろう多くのファンのためにも、それが実現することを祈るばかりである。
日露青年交流センター Japan Russia Youth Exchange Center
このページの文章、画像等一切の無断使用を禁止します。また、リンクを張る際は必ずご連絡下さい。
All right reserved, Copyright(C) Japan Russia Youth Exchange Center 2000
関連タグ
オススメ記事
All right reserved, Copyright(C)
Japan Russia youth Exchange Center 2000-.